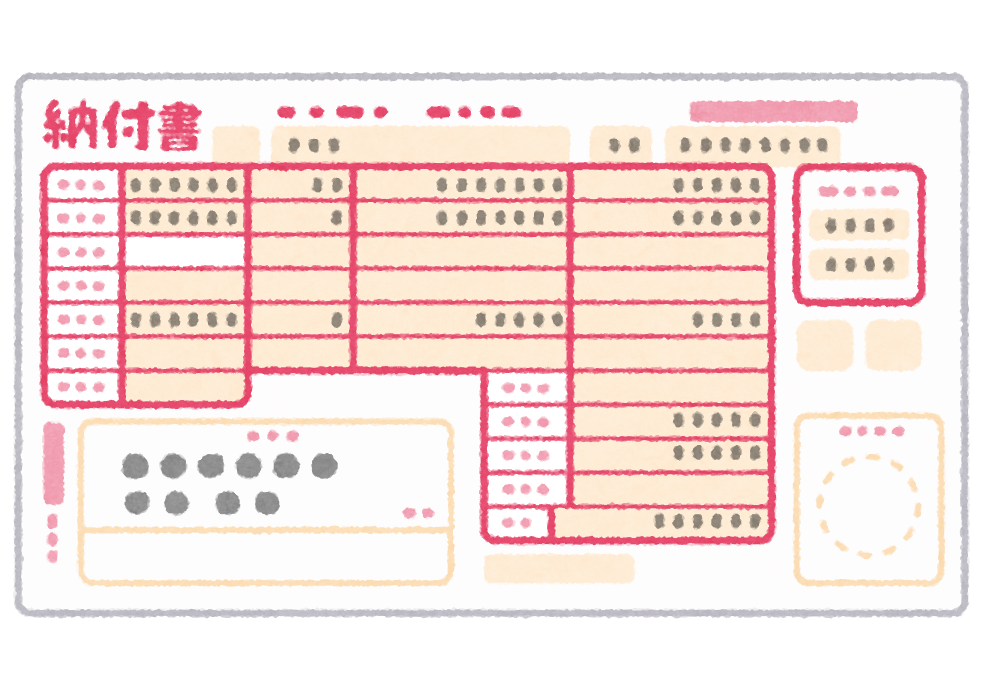6月給与計算から定額減税開始

令和6年6月から給与(または賞与)計算において、定額減税による控除(月次減税事務)が実施されます。

控除対象者ごとの月次減税額は、次の計算式で求めます。
30,000円×(本人+扶養親族等の人数)
6月1日時点の人数で計算します。その後異動があった場合でも、月次の給与計算においては月次減税額の金額の変更は行わない点は注意が必要です。(扶養人数の異動があった場合には、全て年末調整で対応します。
令和6年6月1日以降に支払う給与又は賞与から順次控除していきます。控除しきれない残額については、翌月以降の給与・賞与で残額がゼロになるまで控除をしていきます。誤って引きすぎてしまうと、年末調整で徴収が必要となる場合もありますので、その点は要注意です。
この残額の管理のために、社員毎の管理台帳を作成する必要があります。この管理台帳については、給与計算ソフトを使用している場合には給与計算ソフトで管理できる場合が多く、EXCEL等で手計算している会社の場合には国税庁のホームページからダウンロードできる管理台帳を使用するのが良いでしょう

給与明細書には、実際に控除した月次減税額の金額を以下のように記載します。
【記載例】
定額減税額(所得税)×××円
定額減税 ×××円 など
給与明細のどこに記載するかは、「適宜の箇所」とされており、特に規定はありません。給与明細書に余白がないなど、記載が難しい場合には、別紙に記載しても差し支えありません。
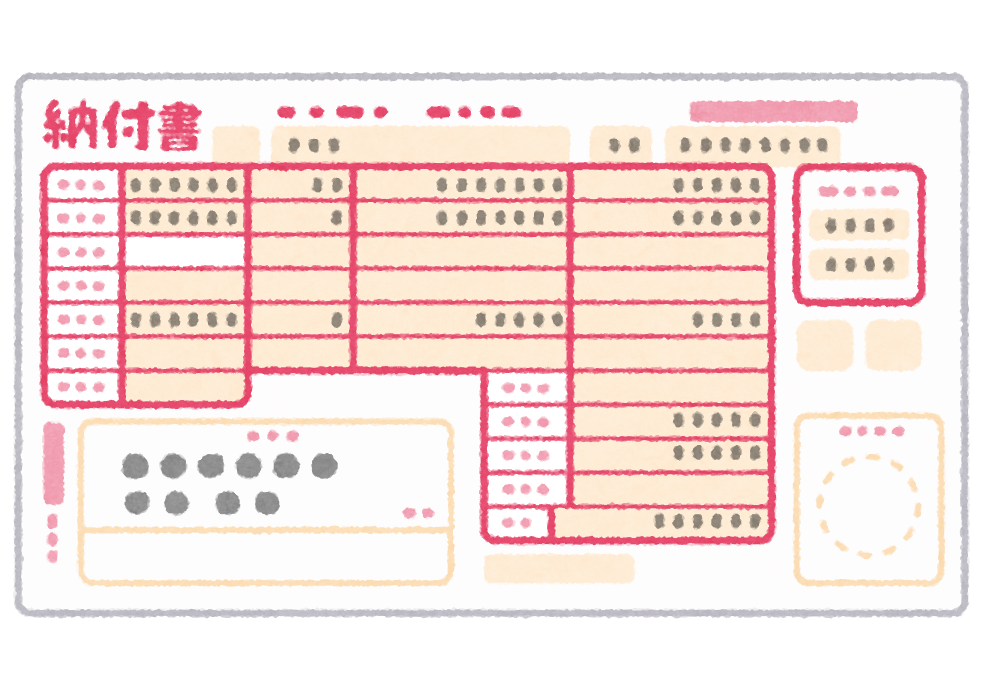
月次減税事務を実施した場合について、源泉所得税の納付書への記載方法は、これまで通りの記載方法で変更ありません。
支給日、支給人数、支給額、源泉所得税額を記載します。
ただし、定額減税の影響で源泉所得税額の欄については、例月、例年に比較して、給与から天引きする金額が減っている分、減少しているはずです。源泉所得税の額がゼロの場合でも、人数や支給額を記載する必要がありますので、記載漏れに注意してください。
住民税については、5月に市区町村から届いた納税通知書上では、既に定額減税が実施された後の金額が記載されていますので、会社側で特別な処理を行う必要がありません。なお、7月10日納付分は基本的にはゼロとなっており、納付する必要はありません。