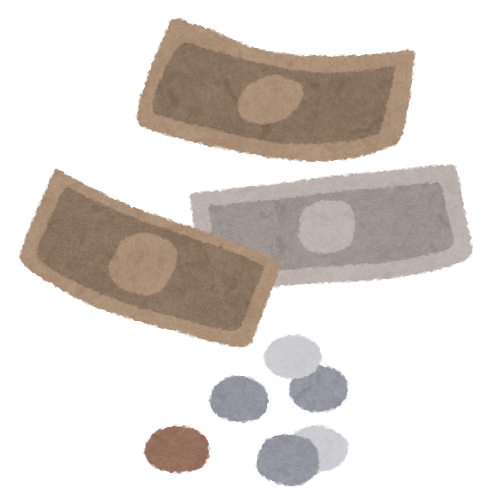賃金のデジタル払いの業者指定

令和6年8月9日に、PayPay株式会社に対し、労働基準法施行規則第7条の2第1項第3号の規定に基づき、賃金のデジタル払いの資金移動業者としての厚生労働大臣の指定が行われました。
PayPay株式会社のプレスリリースによると8月14日よりソフトバンクグループ各社の従業員を対象に「PayPay給与受取」のサービス提供を開始し、また年内にはすべてのユーザーを対象にサービスの提供を始める予定と発表されています。
これにより、これまで金融機関口座への振込が主流だった給与振込に新たな支払方法が生まれました。
(1) 銀行口座へ送金可能(月1回手数料無料)
デジタル払いされた賃金は、月1回手数料無料で銀行口座へ送金することが可能です。これは、労働基準法上、賃金は通貨払いが原則となっているためです。
(2) 第三者保証機関による保証
PayPayのようなデジタル払いを行う資金決済業者が破綻した場合には、保証機関(保険会社等)により速やかに弁済されることとなっています。
(3) 上限額を超過の場合、自動送金(手数料無料)
PayPay給与受取においては、20万円までしか給与残高として受け入れられず、それ以上の給与振込額は指定した金融機関の口座に振り込まれます。
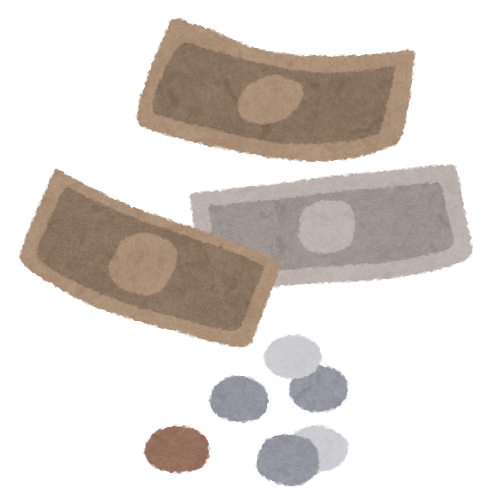
労働基準法上、賃金の支払いについては、「通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定されています。ここでいう「通貨」とは「現金」のこととなります。
現金払いの例外として、これまでは「銀行口座」と「証券総合口座」への支払が認められていました(労働者の同意がある場合)。今回、これに「指定資金移動業者の口座」が追加されたということです。
もちろん、労働者からの同意が必要であり、会社側からデジタル払いを強制されることはありません。

賃金のデジタル払いがどれくらいの期間をかけて、どれくらいのスピードで広まっていくかは分かりませんが、電子化やキャッシュレス化は年々進んできています。
経済産業省のデータによると、2010年に13.2%だったキャッシュレス決済比率(決済額)は、Pay払いが始まった2018年には24.1%、そして、2023年には39.3%と堅調な推移を見せ、「2025年までに4割程度にする」という政府目標をほぼ前倒しで達成している状況です。
キャッシュレス決済で一番割合を占めているのはクレジットカード(決済額で83.5%/2023年)です。交通系ICなどの電子マネーの割合がここ数年ほぼ横ばいのなか、Pay払いなどのコード決済の割合が年々上昇しています。
飲食店やパーキングなど、キャッシュレスオンリー(現金使用不可)のところも目にすることが増え、キャッシュレス決済への対応が不可避な世の中がもう目の前です。