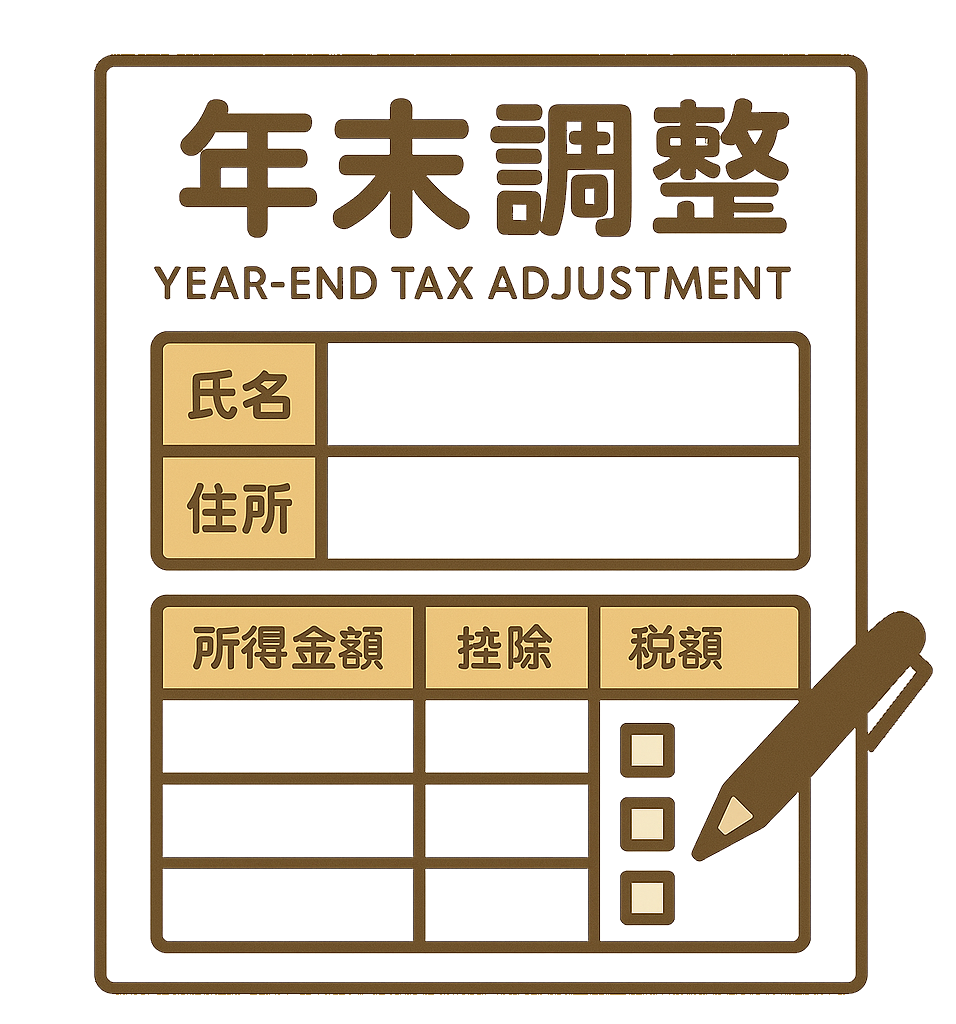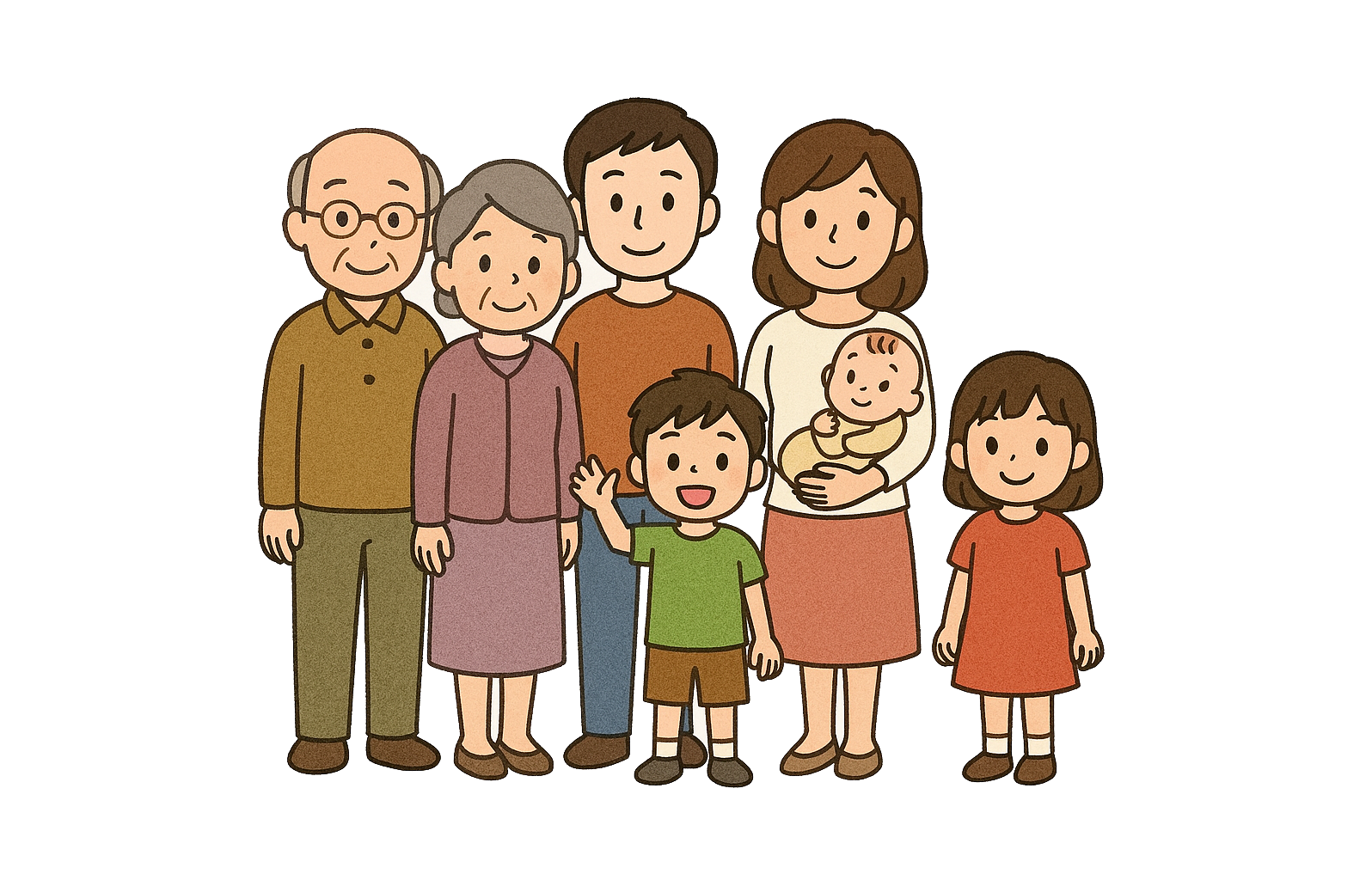令和6年の年末調整
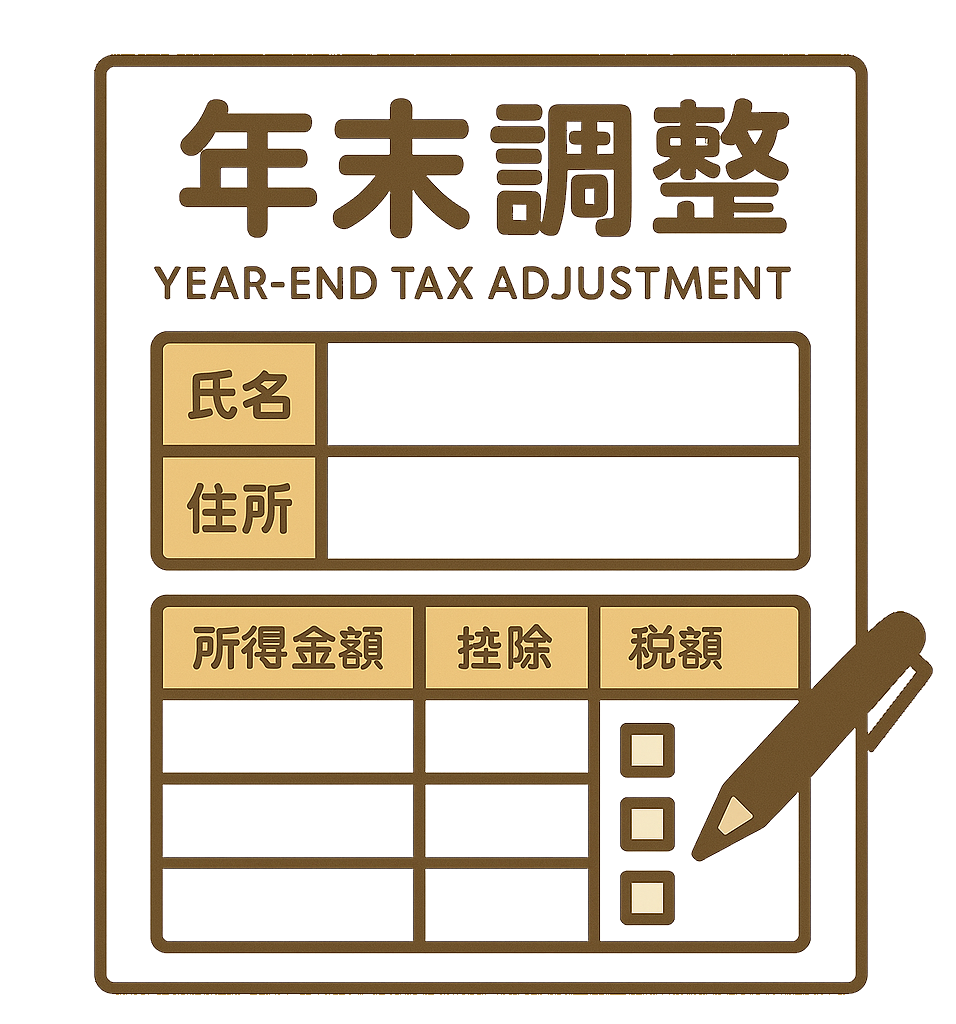
11月に入り年末調整の用紙を従業員に配布する時期になりました。
令和6年の年末調整は昨年までと違い、定額減税の処理が必要となります。これを「年調減税事務」と言います。
年調減税事務では年調減税額を計算し、年間の所得税を計算します。
年調減税額とは年末調整時点の定額減税の額で「本人3万円と扶養家族1人につき3万円」の合計額です。
年調減税事務の対象者となる要件は下記の通りです。
(1)年末調整の対象者
(2)合計所得金額(給与所得以外の所得も含む)が1,805万円以下になると見込まれる
2ヶ所給与など所得税を乙欄で計算している場合以外は、ほとんどの従業員は年調減税事務の対象となると思います。
なお、月次減税事務では、1,805万円超の所得者も対象となり定額減税を行っていましたが、年末調整では対象外となります。
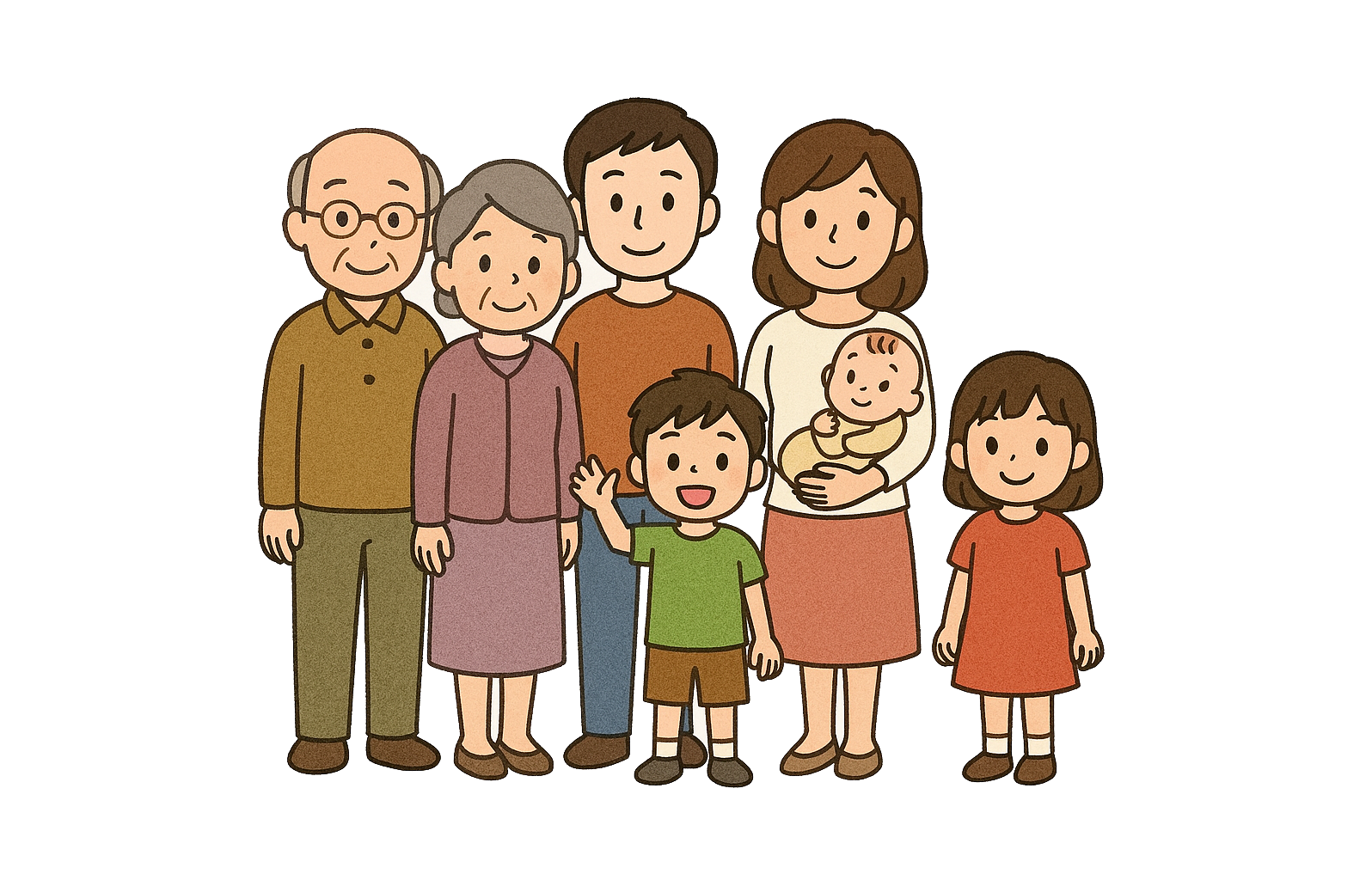
年調減税事務においては、
配偶者や扶養親族の分も本人が定額減税を受けることとなります。
対象となる配偶者・扶養親族は
(1)日本国内に住んでいる
(2)本人と生計を一にしている
(3)合計所得金額が48万円以下になると見込まれる人
(青色事業専従者等を除く)
給与所得のみの場合は、年収103万円以下
給与収入103万円 -給与所得控除55万円=48万円
令和6年分の年末調整の用紙(基・配・所)では、定額減税に関するチェック箇所が2つ増えました。
(1)給与所得者の基礎控除申告書「基・配・所」の年調用紙の左側の部分です。
ここは本人の所得を計算し、それによって「基礎控除の額」と「本人が定額減税の対象か」を申告する欄です。
所得が1,805万円以下になった場合は、「本人定額減税対象」に☑を入れましょう。

(2)給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 年末調整に係る定額減税のための申告書
ここは、配偶者の所得を計算する欄です。
所得の金額によって「配偶者控除」か「配偶者特別控除」となるか、また、配偶者の所得が48万円以下の場合には配偶者を扶養親族として従業員本人の定額減税の対象となります。この場合には「配偶者定額減税対象」に☑を入れましょう。
このように、今回の年末調整は定額減税の対象者かの確認が必要であり、配偶者の所得確認が特に重要となりますので、ご注意ください。